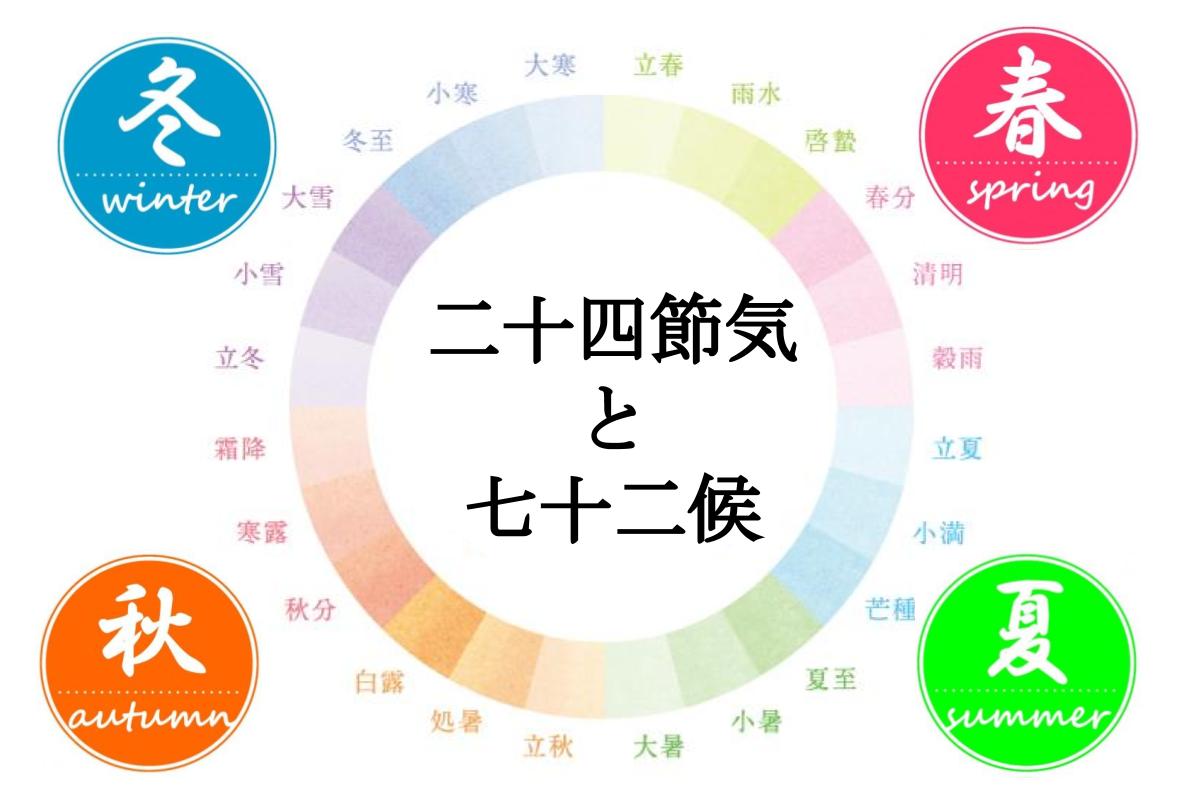二十四節気七十二候(にじゅうしせっきしちじゅうにこう)をカレンダーにしました。
二十四節気(にじゅうしせっき)とは?
一年を夏至・冬至で2等分します
↓ その間を春分・秋分で分け4等分にします
↓ それぞれの中間に立春、立夏、立秋、立冬を入れて8等分します
↓ これを15日ずつ24等分したのが二十四節気
例:立春・雨水(雪が雨に変る)・啓蟄(地中に潜んでいた虫が這い出る)・春分・清明…
一年を夏至・冬至で2等分します
↓ その間を春分・秋分で分け4等分にします
↓ それぞれの中間に立春、立夏、立秋、立冬を入れて8等分します
↓ これを15日ずつ24等分したのが二十四節気
例:立春・雨水(雪が雨に変る)・啓蟄(地中に潜んでいた虫が這い出る)・春分・清明…

このような暦は、天候に左右される農業の目安として大変便利なものでした。
七十二候(しちじゅうにこう)とは?
二十四節気をさらに5日ずつに分け、1年を72等分した暦
例えば 水沢腹堅(さわみずこおりつめる)
桃始笑(ももはじめてさく)
玄鳥至(つばめきたる)
麦秋至(むぎのときいたる)
など
二十四節気をさらに5日ずつに分け、1年を72等分した暦
例えば 水沢腹堅(さわみずこおりつめる)
桃始笑(ももはじめてさく)
玄鳥至(つばめきたる)
麦秋至(むぎのときいたる)
など

季節を知るよりどころでもあったため、天候や生き物の様子を表す名前がつけられています。